
いよいよ2024年7月3日に発行開始が決まった渋沢栄一をデザインした一万円札。
彼は生涯において500もの企業設立などにかかわり、"日本近代社会の創造者"と言われました。
こんにちは。建築ディレクション部の岡田です。
今年の出張研修は「建築」に焦点を当てようと選んだのが、そんな渋沢栄一が初代会長の帝国ホテルです。
建築に興味がある人もそうではない人も、そのディティールを思い浮かべることができるのではないか?と思ってしまうほど有名で、現在も尚「東洋の宝石」として輝く、フランク・ロイド・ライトが手掛けた傑作「帝国ホテル二代目本館」=通称「ライト館」は、1923年に竣工しました。
そして、1969年、宿泊客の増加に伴う客室数の不足と老朽化に伴い、解体されることとなりました。
それは、私が生まれるよりも前のこと。
そのまま解体されていれば、出逢うことの叶わなかったこのライト館は、熱心な保存運動により、中央玄関部分の一部ではあるものの明治村に移築、復元されることとなりました。
およそ17年をかけて1985年より展示公開、現在に至ります。
ライトは「この建物が日本人に理解されるのに半世紀が必要だ」と言う言葉を残したそうですが、ライト館竣工から100年目を迎えた2023年、私が最も敬愛するライトと、中でも最も好きな建築「帝国ホテル」を目指す出張研修を企画しました。
ライトに会いに行く!
企画から約半年後の2024年4月2日(火)快晴。
先週までの悪天候から一転、爽やかな春風とようやく咲き始めた桜、それから、例年に比べ寒過ぎた3月に咲き遅れた桃が美しい道を進み、9:30の開門を待ちきれずに到着。
開門一番に帝国ホテルに最も近い、北口ゲートを潜りました。
拍子抜けするほど、閑散とした道を進むと、これまで何度も紙面で目にしてきた帝国ホテルが雑誌に掲載される写真のままに、圧倒的なスケールで目前に現れました。

それでは、フランク・ロイド・ライトの名建築「帝国ホテル中央玄関」をレポートしたいと思います。
ライトの代名詞=幾何学模様

ライトと言えば、幾何学模様のデザインが特徴ですが、日本の文化や伝統、芸術、建築に深い関心を持っていたライトが「尊ぶべき日本の姿を体現した」と語っていることからも、日本人の私にとって親和性の高い造形だと考えられます。
また、水平性と深い軒、左右対称のデザインは宇治に生まれ育ち、幼い頃はもちろん、大人になってからも、度々訪れては、その美しさに見とれる「平等院鳳凰堂」がモチーフになっていることからも、私がこの建物に強く惹かれる所以かも知れません。
細部のディティールにスポットをあてる

幾何学模様が装飾された大谷石、

それまで一般的に用いられていた「赤い」煉瓦ではなく、「黄色」い「スダレ煉瓦(のちのスクラッチタイル)が採用されています。

そして、私がこの建物の造形の中でも最も好きな装飾テラコッタ。
これらの黄色い煉瓦やテラコッタを焼くために、常滑に専用工場「帝国ホテル煉瓦製作所」が作られました。
この技術や設備を引き継いだのが、伊奈製陶所(のちのINAX、現LIXIL)です。

天井を見上げるとここにも装飾テラコッタのモールが見えます。

軒もド迫力の造形です。
このように随所に様々な造形がみられました。
それら一つ一つはとてもデコラティブで迫力のあるモノばかりですが、
抑えられた色彩と自然素材、そして建物そのもののスケールの大きさから、遠くから見た全体バランスはもちろんのこと、至近距離で見ても、ため息が出るほどの美しいものでした。
正に「建築」が「総合芸術」であることを再認識させられました。
静かなメインロビーへ

エントランスは天井が低く抑えられています。
それは、正面階段を上がった時の、より大きな解放感を演出するためなのだとか。
この高低差の演出は今後の設計に投影したいと考えています。

メインロビーは3Fまでの吹き抜け空間で、外観同様に大谷石とテラコッタの造形に圧倒されます。


中でも照明と装飾(=テラコッタ×大谷石)、構造体が一体となった「光の籠柱(かごばしら)」は、その魅力を表す言葉も見つかりません。
是非、この言葉に出来ない感覚を皆さんにも体験して頂きたいです。
木製建具とステンドグラス


木製建具と金箔を挟み込んだステンドグラスは、全体の建築と調和が取れているというだけでなく、窓外の景色を邪魔しない、建物そのものだけではなく、外部との調和も計算されています。

予算オーバーで解雇
敬愛してやまないライトですが、実は帝国ホテルの完成まで携われていなかったそうです。
その原因は、予算と工期の大幅な超過。
私たちも、常に建築へのこだわりと予算と工期のバランスに頭を悩ましていますが、もしもいま、ライトと仕事をできたとしても、手放しでは喜べないなぁ。と感じたエピソードです。
博物館明治村を歩く

さて、企画から約半年の間、楽しみにし過ぎたライトの建築に触れ、また一つ人生の夢を叶えることが出来ましたが、博物館明治村(通称:明治村)はこれだけではありません。
江戸時代に人工的につくられた日本第2位の大きさを誇るため池=入鹿池に面した約100万㎡の広大で美しい風景の丘陵地に、11件の国の重要文化財を含む67件の建造物が移築、保存されています。
この広大で高低差のある村内を鈍った身体に鞭打ち、重たい一眼レフを抱えて練り歩き、約6時間かけて全制覇しました。
帝国ホテルの他にも見どころはたくさんありますが、そのお話しはまた別の機会に。
旅の締めくくりはライトと共に。

座る人が最も美しく見えるようにデザインされているという六角形の背もたれが特徴的な「ピーコックチェア」に座り、珈琲タイム。
大満足の一日でした。
博物館 明治村
ほかの記事を見る

八清社員が日本各地へ興味が赴くままでかけ、見て、聞いて、普段の業務では得られない知見を広めてきましたのでレポートします。

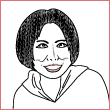

コメント