
今回の出張研修では沖縄県を訪れました。
なぜ出張研修場所に沖縄を選んだのかというと、八清に入社してから、歴史的建築物への関心が高まっただけでなく、学生時代にはあまり興味のなかった歴史にも興味を持つようになりました。
特に、町家が建てられた時代背景を知ることで、その当時の人々の暮らしを想像できる点が非常に面白いと感じています。
そんな歴史的遺産を後世に残すためには、やはり世界平和という考え方が欠かせないと感じています。
今回の研修では、沖縄県の戦争を含む歴史を学び、その歴史的遺産をどのように継承していくべきかを考える良いきっかけにしたいと思いました。
また、沖縄の方々の県民性にも興味があり、穏やかで陽気で幸福度が高いというイメージを持っています。
現地で文化を直接体験することで、沖縄の温かなコミュニティづくりについても学びたいと思います。
さらに、沖縄は山や海などの豊かな自然資産に恵まれています。
それらをどのように活かしてまちづくりを行っているのかについても勉強し、今後の業務や視点に活かしていきたいと考えています。
風除けや防火のために植えられた備瀬のフクギ並木

初日から行きたかった場所は備瀬のフクギ並木です。
沖縄本島北部の本部町に位置し静かな時間が流れる癒しのスポットです。
このエリアは、約300本ものフクギの木が生い茂り、まるで緑のトンネルの中を歩いているような感覚を味わえます。
もともと防風林として植えられたフクギの木々は、台風から家々を守る役割を果たしてきましたが、現在では沖縄らしい景観を楽しめる観光地として親しまれています。
並木道の周辺には赤瓦の古民家や、沖縄らしい伝統的な集落が点在し、昔ながらの沖縄の生活風景を感じることができます。
今回はレンタサイクルでのんびり回りました。
また、すぐ近くには美しい海が広がっていて、フクギ並木と海のコントラストもとても良い景色でした。
自然と歴史、そして穏やかな空気を同時に感じられる場所でした。
アメリカ統治時代の影響を色濃く残す場所

その後、アメリカ西海岸を彷彿とさせるショッピングエリアのアメリカンビレッジに移動しました。
戦後のアメリカ統治時代の影響を色濃く残し、ショッピングモールやレストラン、カフェ、バーなどが建ち並び、多彩な楽しみ方ができるのが魅力です。
昼間はカラフルで楽しい雰囲気を演出し、夜には美しいライトアップが施され、とても魅了されました。
また、エリア内にはアメリカンテイストのグッズや食べ物が並ぶお店が多く、沖縄にいながら異国の文化を体験できる特別な場所でした。
私は本場さながらのステーキを頬張りました。
さらに、アメリカ文化と沖縄のローカル文化が融合したユニークな雰囲気も楽しむことができます。
歴史や文化を感じながら、非日常の体験ができるスポットなのだなと感じました。
沖縄戦の犠牲者を追悼

今回の出張での大きな研修テーマとして「歴史と平和」を考えることができる平和祈念公園とひめゆりの塔は、ずっと行ってみたかった特別な場所です。
平和祈念公園は太平洋戦争末期の激戦地として多くの命が失われた地に造られています。
広大な敷地内には、戦没者の名前が刻まれた「平和の礎」や戦争の記録を展示した資料館があり、静かな空間の中で命の尊さと平和への願いを深く感じることがでました。
公園から望む青い海は美しくもどこか物悲しさを感じました。
ひめゆりの塔は、戦時中に若い看護学生たちが戦争に巻き込まれ、多くの命を失った悲劇の象徴です。
近くにある資料館では、当時の彼女たちの体験や生活の記録が展示されており、悲惨な戦争の現実を生々しく伝えていました。
この場所を訪れることで、彼女たちがどれだけ過酷な状況に置かれていたかを想像すると胸が痛くなり、戦争がどれだけ多くの人々の人生を奪い、未来を壊したかを改めて実感しました。
今回の訪問を通じて、戦争の歴史をただ学ぶだけでなく、平和の大切さを心から考えさせられました。
過去の出来事を忘れず、二度と同じ悲劇を繰り返さないためにも、このような場所を訪れ、自分自身の中で平和について向き合う時間を持つことの重要性を感じました。
伝統工芸を体験
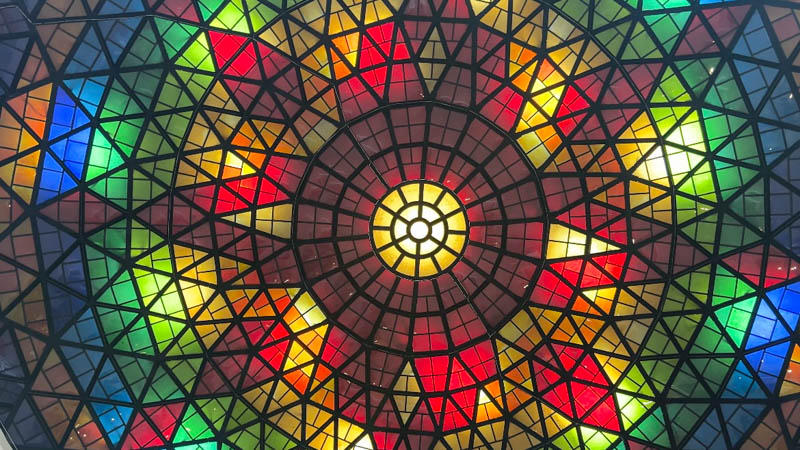
沖縄独自の伝統工芸である琉球ガラスの制作を体験できる琉球ガラス村を訪れました。
ここでは、職人たちが一つ一つ手作りで琉球ガラスを作っています。
色とりどりのガラスが輝き、幻想的な模様やデザインが特徴です。
ガラス作りの体験ができるワークショップもあり、自分だけのオリジナルガラス作品を作りました。

そこで実際に体験して思ったことは、職人の技術力の高さです。
ただ職人の数も年々減っているようです。
建物のものづくりに関しても同様のことが言えると思いますが、職人たちの技術や文化を守り、未来に伝えていく重要性も体感することができました。
沖縄の文化や歴史を知る

沖縄の自然・文化・歴史を丸ごと体験できるおきなわワールドに赴きました。
琉球王朝時代の町並みを再現したエリアでは、伝統工芸や舞踊を楽しみました。

ちゃっかり琉球衣装を着て写真を撮りました。
撮影不可だったのですが、迫力満点のエイサーショーは、沖縄のエネルギーを全身で感じられる感動的なパフォーマンスでした。
那覇の中心に位置する繁華街、国際通り
沖縄県の「国際通り」は、地元文化や観光の魅力が詰まった約1.6kmのストリートです。
「奇跡の1マイル」とも呼ばれ、戦後の復興を象徴する場所としても知られているようです。
国際通りを歩けば、沖縄ならではの音楽やエイサーのパフォーマンスも時折行われており、賑やかで明るい雰囲気でした。
また、地元の人々がよく訪れる島唄ライブでは、隣の席のお客さんとも気付けば自然に交流が生まれ、温かいコミュニティのあり方を肌で感じることができました。
琉球王国時代の中心的な建築、首里城

「首里城」は、琉球王国の歴史と文化を象徴する重要な遺産であり、今回の訪問を通じて多くの学びを得ることができました。

2019年の火災で一部が焼失した首里城は、現在再建に向けた取り組みが進められており、そのプロセスを通じて文化財保護の重要性を改めて考えさせられました。

首里城は歴史的な価値だけでなく、未来に向けた文化保存の取り組みを学ぶ場でもあり、訪問を通じて自分の中で文化財に対する理解が深まりました。
この学びを活かし、文化遺産を守り伝える意識を今後も大切にしたいと思います。
出張研修を終えて
今回の研修を通じて、歴史的建築物から学ぶ日本の歴史の奥深さや、現地の文化に触れることで得た新しい視点を実務に活かしたいと考えます。
特に、首里城の再建プロジェクトで職人たちが伝統技術を駆使し、失われた文化を復元しようとする姿勢は、京都の町家の保全事業にも通じるものがあるのかなと感じました。
また、沖縄の「ゆいまーる(助け合い)」の精神に触れたことで、地域住民や利用者との協力体制を強化し、町家が地域コミュニティに根付く存在であり続けるよう意識する必要があるなと思いました。
さらに、首里城再建の取り組みでは、見学者や地域の人々に復興過程を公開することで、文化財の価値や重要性を広めています。
この姿勢を参考に、弊社が取り組む町家の再生事業でも、修復の背景を発信し、地域住民や観光客がその価値を理解し、共感を得られる仕組みを強化しても面白いのかなと思いました。
今回得た学びを活かし、町家を単なる建物ではなく、文化や歴史を伝える「生きた資産」として守り、地域に貢献する「八清」でありたいと思うようになりました。



コメント