
メディアデザイン部のチョイです。
先日、「タイムスリップ建築探訪」と題した研修に行ってきました。
今回は、江戸時代から令和にかけての建築やまち並みを実際に訪れ、それぞれの時代が織り成す魅力を肌で感じてきました。
訪れたのは、埼玉県川越市、栃木県日光市、東京都青梅市といった個性豊かな地域。
それぞれの時代の建築文化やまち並みに触れることができました。
ここでは、4日間の研修の様子をレポート形式でお届けします。
読んでいる間、少しでもタイムトラベル気分を味わっていただけたら嬉しいです!
小江戸・川越で江戸時代のまち並みと大正ロマンを探る
研修初日の目的地は、埼玉県川越市。「小江戸」という愛称で知られるこの地は、江戸時代の城下町の雰囲気が色濃く残る観光地で、多くの人を魅了しています。

川越駅から少し歩くと、まるで江戸時代に迷い込んだようなまち並みが広がります。
江戸時代、城下町として栄えた川越からは農産物や特産品が江戸へ、江戸からは文化が川越へと行き交いました。

特に「蔵造りのまち並み」として知られる一番街は圧巻。
防火を意識した重厚な造りが特徴的な建物が立ち並び、歴史を感じさせます。
また、川越のシンボル「時の鐘」は、江戸時代から今に至るまで人々の生活を見守り続けてきた存在。
周辺には和菓子屋や雑貨店が軒を連ね、江戸の情緒と現代の生活が融合した不思議な空間が広がっています。
一方、一番街の喧騒を離れた石畳の「大正浪漫夢通り」では、洋風建築が並ぶレトロな雰囲気を楽しむことができます。
昭和初期の趣が漂うモダンな建物たちは、時代の移り変わりを象徴する美しい風景です。江戸から大正へ、わずか一日でその建築様式の変遷を目の当たりにし、それぞれの時代の美しさと機能美に感動しました。
川越のレトロモダン洋風建物・マイベスト3のご紹介

▲山吉ビル(右)、アートカフェエレバート(左)
1. 山吉ビル
昭和11年に竣工した鉄筋コンクリート造の建物で、建築家・保岡勝也の遺作とされる作品。
柱や装飾には古代ギリシャやルネサンス建築の影響が見られ、当時の最先端デザインを伝えています。耐震補強と復元工事を経て、美しい姿がよみがえった名建築です。
2. アートカフェエレバート
山吉ビルのすぐ隣に位置する大正4年建築の和洋折衷の建物で、現在はカフェとして利用されています。
訪れた日は残念ながら定休日だったため中には入れなかったものの、外観だけでも十分にその魅力を感じることができました。
調べると、洋風の外観に土蔵造りの内部を持つ和洋折衷の造りのようで、伝統とモダンが調和した独特の趣がある建物です。
次回訪れる際には、ぜひ内部見学も楽しみたいと思います。
3. シマノコーヒー大正館
大正浪漫夢通りを散策中に見つけた、ノスタルジックな雰囲気漂うカフェ「シマノコーヒー大正館」。
昭和8年に建てられたこの建物は「看板建築」と呼ばれるもので、かつて呉服屋として使われていたそうです。

一目で映画のセットのような愛らしい外観に心を奪われました。
特に、洋館風デザインを引き立てる2階の三連窓、時代を感じるフォントの看板、そして木製の扉の風合いが印象的です。
店内に足を踏み入れると、落ち着いたシックな内装が広がり、ノスタルジックな雰囲気に包まれます。
まるで大正時代にタイムスリップしたような気分に浸りながら、ゆったりとした時間を過ごしました。

ホットコーヒーとキャラメルプリンを注文しました。
プリンは懐かしさを感じるしっかりとした硬めの食感で、濃厚な卵の風味が際立っていました。
心地よい大正時代の雰囲気に癒されながら、疲れがすっと取れるひとときでした。
川越を後にした2日目は、レンタカーで栃木県の日光を目指しました。
日光といえば、国内外に知られる「日光東照宮」を思い浮かべる方も多いと思いますが、実は軽井沢(長野県)や高山(岐阜県)と並び、「国際避暑地」としても名高い場所です。
明治以降、多くの外国人がこの地を訪れ、その文化交流が地域の発展に大きく貢献してきました。
日光東照宮で江戸の工芸美に心震わせる

最初の目的地は、徳川家康を祀る日光東照宮。
ここでは、江戸時代の匠の技が凝縮された豪華絢爛な建築と繊細な彫刻が見事に調和しています。
象徴的な彫刻である「眠り猫」や「三猿」をはじめ、境内全体から感じられる荘厳なエネルギーには圧倒されるばかり。
細部に宿る職人技を目にするたびに、何世代にもわたる努力と情熱が形となって今に伝わっていることを実感しました。
歴史の重みと美しさが一体となったこの空間で、心が震えるような感動を味わいました。
中禅寺湖で国際避暑地の歴史を歩む

▲男体山と中禅寺湖の紅葉
次に訪れたのは中禅寺湖。
明治中期から昭和初期にかけて、各国の大使や要人が湖畔に別荘を構え、夏になると「外務省が日光に移る」とまで言われた、国際的な避暑地です。

まず向かったのは、英国大使館別荘記念公園。
これは明治29年にイギリスの外交官アーネスト・サトウ氏が建てた別荘で、120年の歴史を経て2016年から一般公開されています。
館内では、奥日光が国際避暑地として発展した背景や当時の英国文化、サトウ氏がこの地を別荘に選んだ理由などが紹介されています。

▲2階広縁から眺める湖の景色
また、別荘の2階には湖を望むティールームがあり、絶景を眺めながら紅茶を楽しむことができ、優雅な過去を体感することもできます。

続いて隣接するイタリア大使館別荘記念公園へ。
こちらはチェコ出身の建築家アントニン・レーモンド氏が設計し、昭和3年に完成した別荘です。
平成9年まで歴代のイタリア大使が夏季に使用していたこの建物は、現在では当時の生活様式を再現した家具や調度品が展示され、避暑地としての賑わいを伝えています。
特に印象的だったのは、日光杉の樹皮と薄板で構成された市松模様の外壁。
その美しいデザインは自然との調和を感じさせます。
湖に面したテラスからの眺めは息をのむほど素晴らしく、自然と建築が織り成す見事な景色に心を奪われました。

ここで中禅寺湖を後にし、夕方には日光駅に立ち寄りました。
明治期に建てられた洋風建築の日光駅舎は、優美な佇まいとノスタルジックな雰囲気が印象的で、観光の締めくくりにふさわしいスポットです。
駅の待合室や装飾のディテールには、歴史的建築の魅力が詰まっており、一瞬で時代を遡るような感覚を味わいました。

ここでぜひ注目していただきたいのが、駅舎エントランスの天井に描かれた龍の絵です。
実はこの「日光駅の鳴龍」、日光東照宮の「鳴龍」にインスパイアされたものだとか。
エントランスの格子状の天井に隠れるように描かれた龍を見つけたときは、小さな発見に胸が躍りました。
早速、手をたたいて試してみましたが...残念ながら鳴き声を聞くことはできませんでした。
それでも、このユニークな装飾に触れることで、日光の最後に思い出深いエピソードをひとつ追加できたように思います。
自然と星空に癒されるオールインクルーシブホテル

中禅寺湖の散策を終え、その日の宿泊先である「TAOYA日光霧降」へ向かいました。
「TAOYA日光霧降」は、近年注目を集めているオールインクルーシブホテルです。
宿泊料金には食事や飲み物、アクティビティなどの施設利用料がほぼ含まれており、追加料金を気にせずにゆったりと過ごせる点が大きな魅力です。

▲ドリンク・スナックなども別料金なしで楽しめる暖炉ラウンジ
ホテルは霧降高原の標高1,000mに位置し、四季折々の自然が広がるロケーションにあります。
高山植物の宝庫としても知られるこの地では、自然観察や星空鑑賞といった多彩なアクティビティが用意されています。
当日はあいにく星空鑑賞ツアーに参加できませんでしたが、露天風呂から見上げた夜空はまさに特別な光景でした。
遮るもののない満天の星を眺めながら温泉に浸かる時間は、心も体も癒してくれる特別なひとときでした。
翌朝は、ホテル内で朝食を楽しんだ後、自然観察ツアーに参加しました。
散策路では、スタッフの丁寧な解説とともに多種多様な草花に触れ、自然の奥深さを改めて実感。
都会育ちの私にとって、このような体験はとても新鮮で印象深いものになりました。

▲ガイドスタッフさんの解説を聞きながら森林浴。いい朝散策となりました。
自然と調和した美しい環境に、現代的な快適性が見事に融合したこのホテルでの滞在は、心身をリフレッシュさせる貴重な体験。
ゆっくりと流れる時間の中で、贅沢なホテルライフの魅力を存分に味わうことができました。
昭和レトロのまち並みを歩き、青梅市へ

研修の最終日には、栃木から東京へ戻り、近郊の青梅市を訪れました。
学生時代から昭和レトロな雰囲気に憧れていた私にとって、「昭和レトロの発祥の町」とも言われる青梅市での散策は、昭和の時代へタイムスリップしたような感覚に心が躍るようワクワクしてきました。
JR青梅線の青梅駅に降り立つと、プラットフォームから改札へ続く地下通路には、昭和の時代を思い起こさせるような懐かしい空気が漂っています。
両脇に並ぶクラシックな看板がその空間を彩り、駅を出た先に広がる商店や道端の看板には、日常の風景の中に昭和の記憶が残っていました。

▲路地の入口にある、名作映画「ローマの休日」をテーマにした紙店の看板
かつて江戸へ続く街道として栄えた「青梅街道」沿いに発展した宿場町「青梅宿(おうめじゅく)」があったこの地。
現在は「旧青梅街道」という名前で知られる通りに、レトロな建物が点在し、散策スポットとして人気を集めています。
昭和の温もりと懐かしさが残るまち並みを歩くと、心がほっと和むような気持ちになりました。

特に印象的だったのは、「昭和レトロ商品博物館」。
大正末期に建てられた木造2階建ての建物は、かつて家具屋として使われていた歴史あるもの。
現在は、「昭和の賑わいを青梅商店街の活性化に繋げたい」という思いから改装され、ユニークな博物館として生まれ変わりました。

▲まるで昭和時代にタイムスリップしたような昔の駄菓子屋コーナー

▲文房具、生活雑貨、医薬品...カテゴリーごとに並べられたショーウインドー
館内には、昭和30年~40年頃のお菓子や薬の商品パッケージをはじめ、当時のポスターやおもちゃ、ドリンク缶といった生活雑貨が所狭しと展示されています。
商品パッケージのデザインはどれもかわいらしく、見ているうちに昭和の時代へ引き込まれるようなワクワクした気持ちになりました。

さらに、館内には「最後の映画看板絵師」として知られる久保板観さんの手描き映画看板を展示するスペースもあり、昭和時代の文化がいきいきと蘇ります。
昭和レトロ商品博物館では、展示物を通じて昭和の暮らしや価値観が生き生きと感じられ、一つひとつの品物がその時代の物語を語りかけてくれるようでした。
訪れるたびに新たな発見があり、昭和という時代がいかに人々に愛されてきたかを再認識することができました。
昭和レトロ商品博物館から帰ろうとした際、スタッフの方に研修の趣旨をお伝えしたところ、「ぜひ津雲邸も訪れてみてください!」と勧められました。
本来は一般公開されていない津雲邸ですが、ちょうど特別企画展が開催されているため、運良く内部を見学することができました。
伝統とモダンが織りなす昭和の邸宅

博物館からほど近い坂の途中に佇む津雲邸。
昭和初期、青梅市出身の政治家・津雲國利が建築したこの入母屋造の邸宅は、京都や地元の職人が手がけた純和風建築に、西洋近代のモダンな要素を巧みに取り入れた趣深い佇まいが特徴です。

▲1階の応接間。訪問当時は天袋の戸、掛軸、大奥の浮世絵などの様々なアートを展示されていました。
昭和初期から戦後にかけて政府高官や著名人が訪れた歴史的なこの邸宅は、2020年に国の登録有形文化財に指定されました。
母屋だけでなく、外堀や門も指定された点は非常に貴重とされています。
当日は、係員の方が邸内の詳細について丁寧に解説してくださり、職人技が息づく建築の細部や、文学や芸術の息吹が感じられる空間を存分に堪能しました。

▲柔らかな陽光に包まれ、静謐な雰囲気が漂う茶室。

▲廊下の大正ガラスの窓や、蝶をモチーフにした欄間が美しい。

▲格式高い二重格天井の設えが印象的な、書院造りの大広間。

▲奥多摩の山々を一望できる大広間の縁側。

▲青梅がかつて夜具地の名産地であったことを示す展示も見られます。
時間を忘れるような静謐な空間に包まれた津雲邸は、まるで時を超えて語りかけてくるかのようでした。その歴史的価値と美しい佇まいは、青梅市を象徴する存在と言えるでしょう。
新たな魅力を生み出す青梅市のまちづくり
青梅市で感じた昭和建築の温かさと力強さ。それは単なる懐古ではなく、時代を超えて人々を引きつける普遍的な魅力を備えています。
一方で、青梅市は「ノスタルジーを売る」だけにとどまらず、近年、新たな取り組みを積極的に行っています。

かつてまちのシンボルだった手描き映画看板は、2018年に制作者が逝去したことや台風被害による安全面の懸念から撤去されました。
しかし、その後、地域を盛り上げる新たなテーマとして「猫」が注目されました。商店街では猫をモチーフにした商品やオブジェが取り入れられ、まち全体が「猫町」の雰囲気を演出しています。
昭和の懐かしさと猫の愛らしさが共存する青梅市のまち並み。
時代の移り変わりを感じつつも、変わらぬ魅力と新たな工夫が、訪れる人々の心をつかんでいます。
最後に
今回の研修では、江戸から令和に至るまでの多様な建築様式や文化的背景に触れ、それぞれの時代の魅力を改めて実感しました。
川越の城下町の情緒、日光の国際的な避暑地としての洗練、青梅の昭和レトロな温かみ―それぞれの地域が持つ独特の空気感に浸りながら、過去と現在が見事に調和する日本の美しさを再発見するチャンスとなりました。
また、訪れた建築やまち並みが当時の人々の暮らしや価値観を映し出し、歴史と文化の奥深さを体感できたことも、大きな収穫でした。これからは、過去を尊重しつつ未来へと繋げる視点を大切にしながら、自分の仕事にも活かしていきたいと思います。
皆さんもぜひ、日々接する建物やまち並みを通じてタイムスリップ気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。

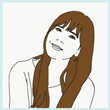

コメント